東京科学大学・獨協医科大学との共同研究により、遠隔介入型ヘルスケアアプリ「Koji Awareness™」の臨床研究成果を発表
2025年10月、第29回日本遠隔医療学会学術大会(大会公式サイト)において、東京科学大学 副学長 室伏広治氏、獨協医科大学埼玉医療センター 准教授 片桐洋樹氏、株式会社アクシス 代表取締役 宮腰行生が、共同研究によるIoTアプリケーション「Koji Awareness™」に関する臨床研究成果を発表しました。

「Koji Awareness™」アプリについて
「Koji Awareness™」アプリは、身体機能の自己評価と改善運動を自動で提案するIoTアプリケーションです。
Koji Awareness™は、室伏氏が現役時代に培った経験と、大学での基礎的研究や臨床研究の成果を土台にして開発されたもので、年齢や場所を問わず、誰もが自分のからだの状態に気づき、改善し続けることができる新しいヘルスケアメソッドです。
このKoji Awareness™を、特別な場所や運動器具を必要とせず、誰もが自宅や職場など好きな場所で、気軽にセルフチェックや、その人に適した改善エクササイズができるようにしたものが「Koji Awareness™」アプリです。
ユーザーはアプリを通じて自らの身体機能を計測し、アプリは分析データに基づき、個別化された改善運動を提案・管理します。
これにより、医療機関や運動施設に行かずとも、自宅などで安全かつ科学的根拠に基づく運動介入を受けることが可能になります。
アプリはからだ可動性年齢™(KAスコア)を指標とし、可動域・疼痛・倦怠感などの改善効果を可視化することで、モチベーションの維持と継続利用を促す仕組みを備えています。

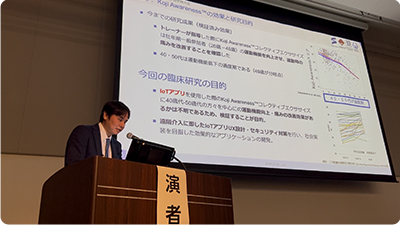
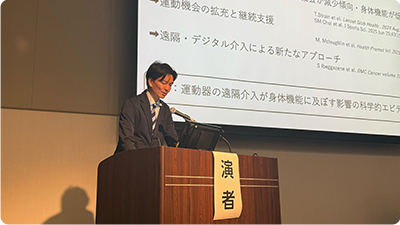
弊社発表概要
| 発表演題 | 「IoTアプリケーション『Koji Awareness™』における遠隔介入のためのアプリUX設計・セキュリティ対策・利用分析」 |
| 発表者 | 宮腰行生(株式会社アクシス 代表取締役) |
| 共同研究機関 | 東京科学大学、獨協医科大学、新潟医療福祉大学、早稲田大学 |
本研究は、運動器機能の低下を社会課題と捉え、遠隔介入によるヘルスケアの社会実装を目指したものです。科学的エビデンスに基づく運動器セルフチェック・改善アプリ「Koji Awareness™」を中心に、UI/UX設計、継続利用を支えるゲーミフィケーション、セキュリティ設計を含むIoT実装技術を開発しました。

臨床研究で得られた成果
- 痛みの改善を53%、可動域の改善を68%、倦怠感軽減を46%の被験者が実感
- アプリ操作性について80%以上が「わかりやすい」と回答
といった有意な効果が確認されました。
また、継続的な利用を支える仕組みとして、スコア可視化「からだ可動性年齢™」などを利用し、一定のモチベーション維持が確認できました。
今後の展開と社会実装への展望
今後は、これらの成果を基盤として、遠隔介入を実現するIoTアプリケーションとしての社会実装を2026年度以降に本格化する予定です。
具体的には、地方自治体や医療機関との連携を通じて、高齢者・運動器疾患リスク層を対象とした「セルフチェックによる予防支援モデル」の確立を目指します。
株式会社アクシスについて
株式会社アクシスは、医療・スポーツ・テクノロジーを融合した健康支援サービスの開発を推進し、科学的根拠に基づくアプリケーションの社会実装を通じて、健康寿命延伸と生活の質の向上に貢献しています。
